「日本史の勉強が苦手…」
「教科書を読んでも頭に入らない…」
そんな悩みを抱えている中高生や受験生の方はいませんか?実は、日本史の成績を上げる上でカギとなるのが「資料集(図説)」の活用です。
資料集は、文字だけでは伝わりづらい歴史の流れや文化の変遷を、図や年表、地図などで“視覚的”に理解させてくれる便利な学習ツール。特に近年の大学入試では、資料をもとに考察させる問題も増えており、「読解力+資料読解力」が求められています。
しかし書店には多くの資料集が並び、「どれを選べばよいか分からない…」と迷う方も多いのが現実です。そこで本記事では、現役塾長の視点から本当におすすめできる「日本史資料集・図説」を厳選して5冊ご紹介。さらに、効果的な使い方や学習法も後半で詳しく解説していきます。
あなたの勉強効率を飛躍的に上げる1冊が、きっと見つかるはずです!
日本史資料集図説おすすめランキング5選
日本史の理解を深め、記憶の定着を助けてくれる「資料集(図説)」は、教科書とは別に必ず手元に持っておきたいアイテムです。特に図説は、視覚的に情報を得られるため、記憶にも残りやすく、文化史や年号の整理に強くなれます。
ここでは、学習塾でも実際に使用され、受験生や指導者から評価の高い資料集を5冊厳選して紹介します。
おすすめ1位:詳説日本史図録(山川出版社)
「これを持たずに受験に挑むのは、裸で戦場に行くようなもの」――そんな声が上がるほど、日本史学習の必需品とされているのが、山川出版社の『詳説日本史図録』です。
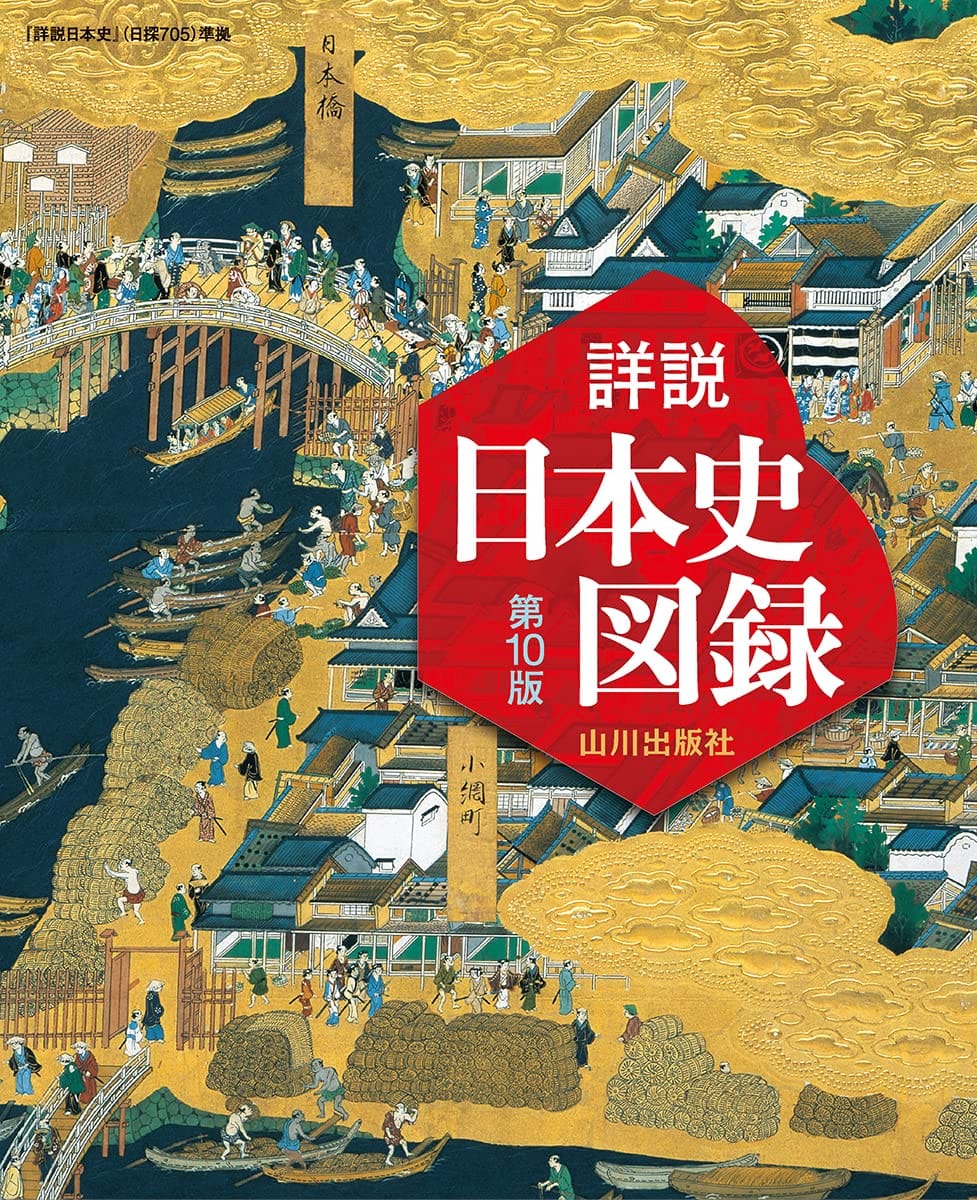
全国の高校で採用される圧倒的シェアと信頼性、そして1,000円以下とは思えないほどの充実した内容。全ページフルカラーで、地図・年表・肖像・文化財・仏教建築・条約文書まで、まさに“日本史の百科図鑑”ともいえる完成度です。
近現代史の情報量も桁違いで、東京書籍などの他社製品では物足りなかった読者から「こっちに変えて正解だった」と絶賛されています。仏教や寺院に興味のある人には特におすすめで、時代ごとの宗派の流れや建築様式の違いまで図解で一目瞭然。観光や御朱印巡りの参考にもなる一冊です。
さらに最新版では、QRコードから動画解説まで視聴可能。教科書の補足だけでなく、“点”の知識を“線”に変える力が、この一冊にはあります。中学受験生から大学受験生、大人の学び直しまで──どの世代にも胸を張ってすすめられる一冊。今すぐ手元に置くべき、歴史学習の最強バイブルです。
おすすめ2位:図説 日本史通覧(浜島書店)
「いくら覚えても日本史がつながらない…」そんな悩みを持っているあなたにこそ、『図説 日本史通覧』を手に取ってほしい。この一冊は、“断片的な知識”を“つながりある理解”へと変えてくれる、日本史学習の再構築ツールです。
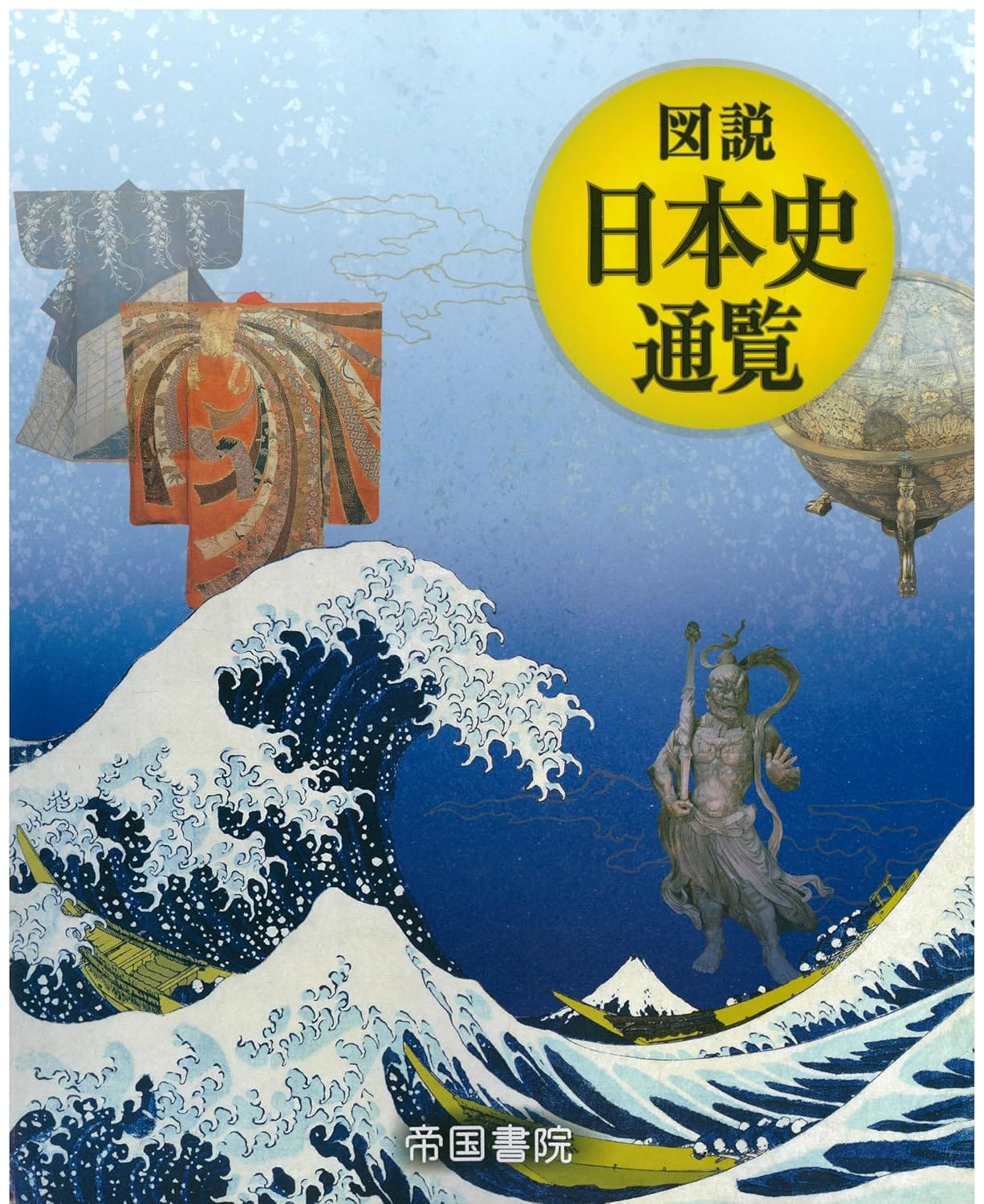
浜島書店が誇る本書の強みは、なんといってもその圧倒的な“図解力”。地図、年表、系図、図版がページごとに息づき、たとえば東アジアの情勢や日本列島各地の文化圏が「一目でわかる」ようにまとめられています。「教科書では理解できなかった戦国時代の勢力図がスッと入った」「都市ごとの産業の違いが可視化されて整理できた」──そんな声も多数寄せられています。
さらに、教科書に載っていないマニアックな史料や図解も豊富で、私大の記述問題や論述対策にも直結。語句索引も充実しており、知らない単語もすぐに調べられるのは、留学生や社会人の学び直し勢にも高評価のポイントです。
“とりあえず一問一答”の時代は、もう終わり。
本気で日本史を「理解」したいなら、今この瞬間から『図説 日本史通覧』を開いてください。
おすすめ3位:新詳日本史(浜島書店)
「ただ覚えるだけの日本史は、もうやめにしませんか?」
受験生の多くがつまずくのは、“歴史の流れ”と“背景”を理解しないまま、暗記に走ってしまうこと。そんな悩みに刺さるのが浜島書店の『新詳日本史』です。
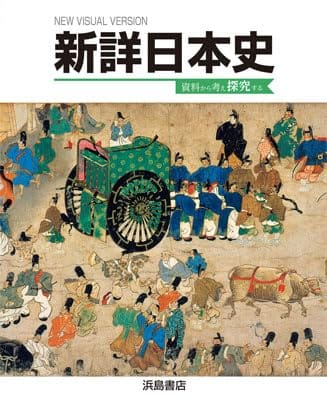
この一冊は、図と解説が絶妙に融合された“理解型”資料集。イラストや写真、図解がページ全体に溶け込み、教科書では見落としがちな「なぜ?」を丁寧に解き明かしてくれます。
たとえば、武士の装備や寺社の構造といった細部まで図で確認できるので、文化史の得点源化にも直結。さらに、法制度の変遷や外交関係などもテーマ別に整理されており、論述や記述問題への対策もバッチリです。
「わからない」を「わかる」に変える鍵が、ここにあります。あなたの日本史の世界を塗り替えるなら、次に開くページは『新詳日本史』で決まりです。
おすすめ4位:日本史資料集(日能研ブックス)
「歴史はストーリーだ」──この言葉にピンときたあなたには、日能研ブックスの『日本史資料集』がぴったりです。
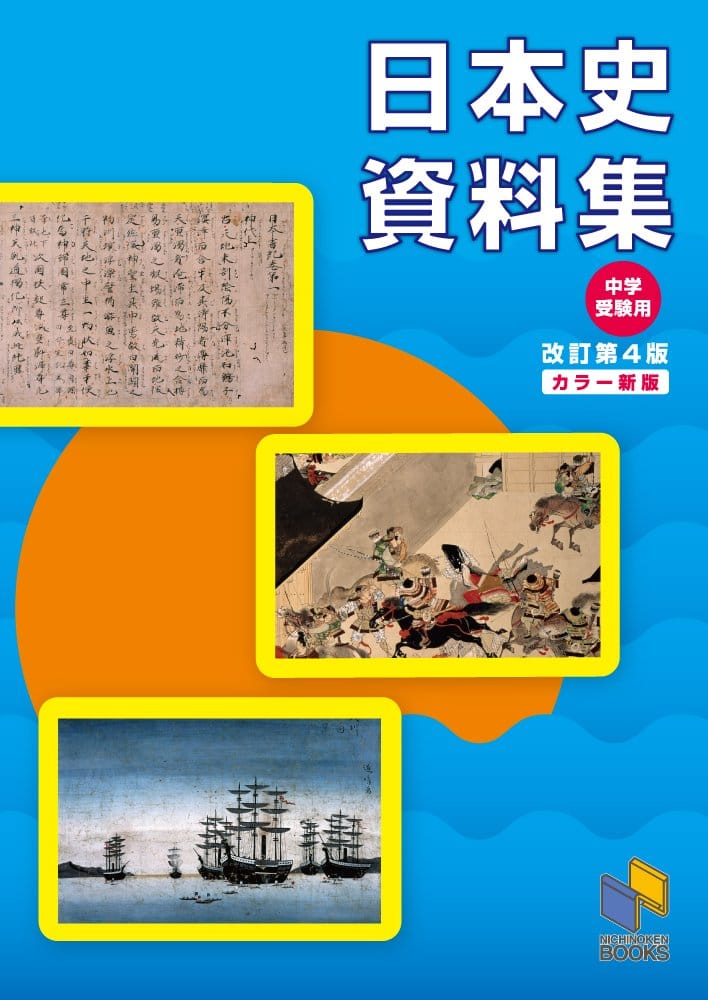
本書は、単なる年号暗記ではなく、「なぜその出来事が起こり、どうつながっていくのか」を“流れ”として理解できるよう構成されています。図解・地図・イラストがバランスよく配置され、まるで一冊の歴史絵巻を読んでいるかのようにスッと頭に入ってくる。暗記が苦手な人や、歴史を丸ごと把握したい人にはまさに理想的な一冊です。
しかも、各時代の要点がコンパクトに整理されており、忙しい受験生が短時間で復習したいときにも最強の相棒になります。入試頻出の資料や地図にはアイコン付きでマーキングされているため、「どこを押さえれば点になるか」が一目でわかるのも高評価ポイントです。
また、親子で一緒に使える“教養書”としての完成度も抜群。実際、学び直しを目指す大人の読者からも「分かりやすくて面白い」と絶賛されています。
ストーリーで理解し、視覚で定着させる。
この一冊を持たずに、どうやって受験に挑みますか? “読みやすさ”と“得点力”を両立した、コスパ抜群の資料集。今、選ばない理由はありません。
おすすめ5位:歴史資料館 日本史のライブラリー
「覚えるだけの日本史」で終わっていませんか?
いま、大学入試は“思考力”重視の時代に突入しています。その波にしっかり乗るために、あなたに必要なのは“考える日本史”に変えてくれる一冊──それが清水書院の『歴史資料館 日本史のライブラリー』です。
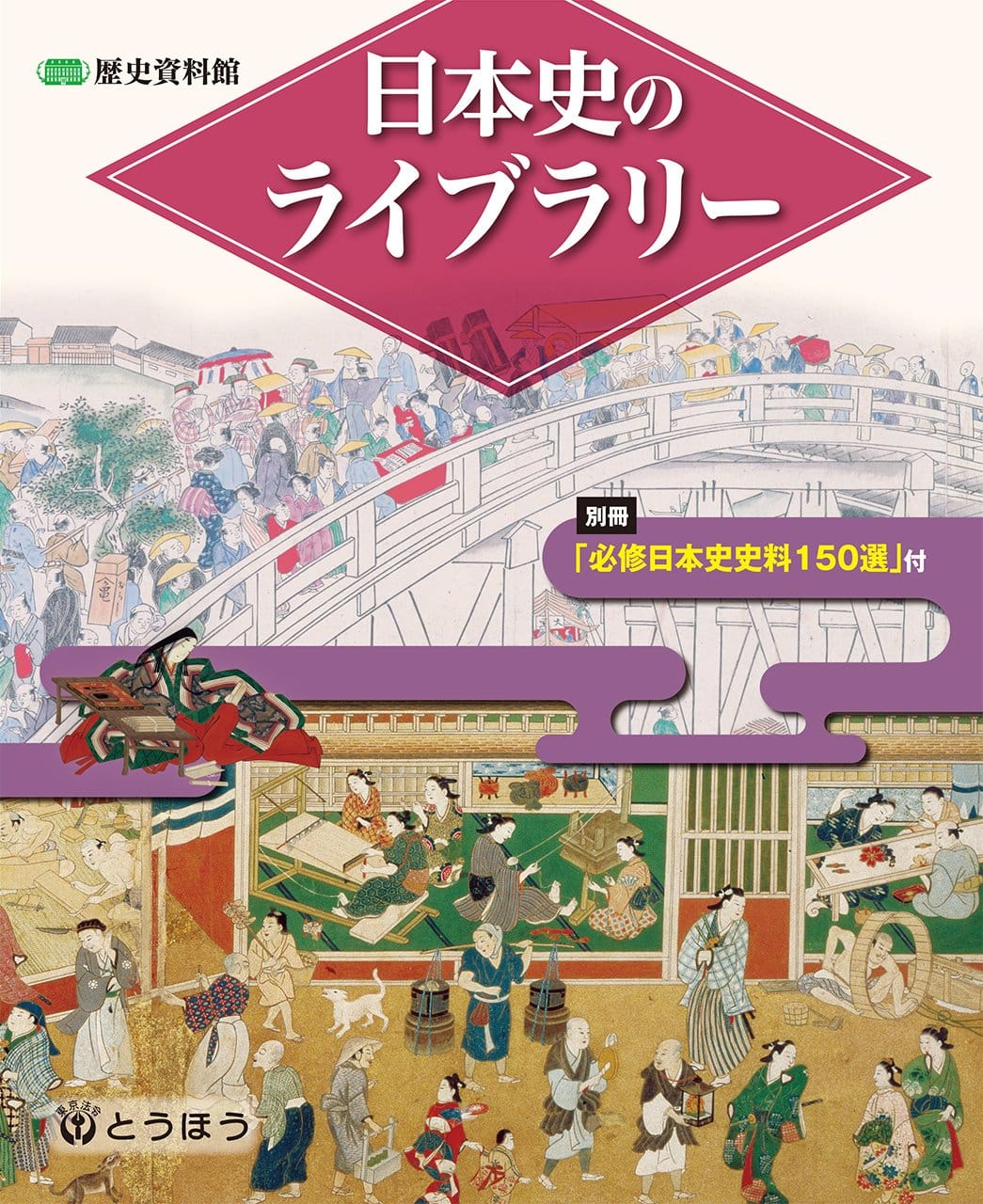
この資料集は、史料の原文や図像資料を数多く掲載し、ただの「知識の暗記本」では終わらない構成。地図、絵巻、浮世絵、法令文書など、リアルな史料を通して歴史の“空気感”をつかめる作りになっています。各ページには「読み解く問い」が仕込まれており、センター試験(共通テスト)や国公立二次の記述問題を攻略するための“実戦力”が自然と身につきます。
巻頭の特集や、訪ねてみたい歴史都市の紹介、史跡地図の巻末資料など、知的好奇心を刺激する仕掛けも満載。「日本史が好き」だけでは終わらない、「日本史で得点する」ための設計がこの1冊には凝縮されています。
「記述に弱い」「資料問題で点が取れない」──そのまま放置して受験本番を迎えますか?
今こそ、“思考型資料集”を手に取り、差がつく日本史力を身につけましょう。
日本史資料集図説おすすめランキングの後に:使い方のコツ
おすすめ資料集を手に入れたら、あとは使いこなすだけ。しかし「ただ眺めているだけ」では、その効果は半減してしまいます。資料集は使い方次第で、“日本史の成績を劇的に伸ばす”強力な武器になります。
ここからは、資料集を最大限に活かすための「5つの使い方のコツ」を、具体例を交えて解説します。
教科書と資料集はセットで使うのが基本
日本史が苦手な人の多くが、「出来事を単体で暗記している」状態に陥っています。たとえば「廃藩置県」を“明治時代に行われた改革”と覚えていても、その前後関係や目的、影響を理解していなければ、記述問題や資料問題では対応できません。
そこで重要なのが、教科書と資料集を並行して使う学習法です。教科書で流れをつかみ、資料集で図解や地図から“背景と因果”を補強することで、歴史が線としてつながります。
特に戦国時代や幕末のように、政治構造や人物関係が複雑な時代は、以下のような“対応表”をつくりながら読み進めると効果的です。
| 学習アイテム | 目的 | 活用例 |
|---|---|---|
| 教科書 | 歴史の時系列を把握 | 「廃藩置県は1871年に実施」など基礎事項の確認 |
| 資料集(図説) | 視覚的に因果関係を理解 | 地図・年表で前後関係を可視化、「なぜ起きたか」「結果は何か」を整理 |
| 自作ノート | 知識の再構成 | 教科書の出来事→資料集の図版→自分の言葉で要約 |
たとえば「日露戦争」の背景なら、教科書で戦争の原因を確認し、資料集で開戦前後の極東情勢を地図で視覚的に把握する。これだけで記憶の定着度は数倍に跳ね上がります。
入試頻出テーマ(戦争・条約・文化史)は資料集で視覚的に強化
共通テストや私大の日本史では、「戦争」「条約」「文化史」といったテーマが頻出です。これらは文字だけで学ぶと混同しやすく、誤答の原因になります。そこで資料集を併用し、図・年表・写真を視覚的に整理することが重要です。
特に戦争と条約は、「起きた順番」と「どの条約でどう終わったか」の対応が問われやすいため、以下のような整理表を作っておくと効果的です。
| 戦争名 | 年代 | 終結条約 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 日清戦争 | 1894〜1895年 | 下関条約 | 台湾割譲・賠償金・朝鮮の独立が確定 |
| 日露戦争 | 1904〜1905年 | ポーツマス条約 | 南樺太割譲・韓国に対する優越権 |
| 太平洋戦争 | 1941〜1945年 | ポツダム宣言受諾 → サンフランシスコ平和条約 | 日本の主権回復・領土問題に関わる |
このように、戦争の背景→条約→影響を視覚的に結びつけておくと、記述問題にも対応できる“つながりのある知識”になります。
また、文化史の強化には図版が欠かせません。たとえば、飛鳥〜鎌倉時代の仏像の様式、建築物の屋根構造、文学作品の表紙などは、文字で覚えるよりもビジュアルの方が圧倒的に記憶に残ります。
資料集には文化財の写真やイラストが多数掲載されており、「見て覚える」「比べて違いを理解する」ことができます。入試では「次の絵の建物はどの時代のものか」といった問題も出題されるため、視覚記憶=得点源になるのです。
一問一答だけでは足りない!図説で“つながり”を補完しよう
一問一答集は、知識を“増やす”には便利ですが、知識を“使えるようにする”には不十分です。理由は明白で、それは“つながり=因果関係”が見えないから。点の知識だけでは、論述問題や資料問題には太刀打ちできません。
ここで頼りになるのが資料集(図説)です。特に効果が高いのが、テーマ別・時代別の整理された図解を用いた学習。たとえば、鎌倉新仏教をただ羅列で暗記しても意味がありません。それぞれの宗派がどの時代背景で、どの層に広がったのかを理解する必要があります。
以下のような表で図説と併用すると、記述対応力が一気に高まります。
| 宗派名 | 開祖 | 時代背景 | 主な教義・特徴 | 広がり方 |
|---|---|---|---|---|
| 浄土宗 | 法然 | 平安末期:末法思想の広がり | 念仏を唱えれば救われる | 貴族から庶民へ浸透 |
| 浄土真宗 | 親鸞 | 鎌倉時代:動乱の時代、救いを求める民 | 絶対他力(阿弥陀仏への信仰) | 農民に広く普及 |
| 日蓮宗 | 日蓮 | 蒙古襲来直後、国難を乗り越える教え | 法華経を絶対視、「南無妙法蓮華経」 | 商工民に支持される |
| 臨済宗 | 栄西 | 宋との交流が活発に | 公案を使った座禅 | 武士階級に広まる |
| 曹洞宗 | 道元 | 宋からの帰国後、日本仏教を改革 | 只管打坐(ひたすら座禅) | 地方武士に受容される |
このように、一問一答の“点”を図説の“線”で補完することで、歴史の理解は格段に深まります。また、図説には時系列年表や文化史の系譜図も豊富に掲載されているため、知識を体系化する上での“地図”として使えるのです。
模試や定期テスト前は“テーマ別復習”に活用しよう
模試や定期テスト前の勉強、何から手をつければ良いか迷っていませんか?
そんな時に頼りになるのが「資料集のテーマ別ページ」です。日本史は“時代の流れ”も大切ですが、入試で問われるのは**「特定テーマを軸にした知識の整理」**です。
特に模試や入試で頻出のテーマを、以下のように「テーマ別+資料集活用法」で分類しておくと、復習効率が飛躍的にアップします。
| テーマ | 出題頻度(目安) | 資料集の活用ポイント | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 外交史 | ★★★★☆ | 条約年表・領土地図・国際関係図 | 日米修好通商条約、三国干渉など |
| 経済政策 | ★★★☆☆ | 政策一覧表・財政制度の図解 | 田沼意次の改革、明治期の殖産興業 |
| 宗教・文化 | ★★★★★ | 仏像写真・建築図・宗派別比較表 | 奈良仏教と鎌倉新仏教の比較など |
| 武士制度の変遷 | ★★★★☆ | 地位の変遷図・封建制度の模式図 | 御恩と奉公・武家諸法度 |
| 女性史 | ★★★☆☆ | 資料中の女性の記述・家制度に関する史料 | 大奥、民法改正、女性参政権など |
※出題頻度は過去10年分の共通テスト・私大入試分析を基にした参考目安です。
多くの資料集では、これらのテーマごとに入試頻出マークや太字強調があり、どこを押さえるべきかが一目で分かります。つまり、“得点直結”の優先順位が視覚的に示されているのです。
さらに、資料集の図や表を参考にしながら自作のテーマ別まとめノートを作成すれば、記憶の定着率も格段に向上します。視覚的に整理→言語化→反復、という流れが完成するからです。
資料集は「読む」だけでなく、「使い倒す」ことで真価を発揮します。
資料集の「資料」は、記述対策や志望理由書のネタにも使える
多くの受験生が見落としがちですが、日本史の資料集は「覚えるための本」ではなく、“書く力”を支える参考書としても活用できます。特に、共通テストの資料読み取り問題や、国公立大学の論述問題、さらには総合型選抜(旧AO入試)や推薦入試の志望理由書でも威力を発揮します。
以下は、入試形式別に見た資料集の具体的な使い方の一例です。
| 入試形式 | 出題傾向 | 資料集活用のポイント | 具体的資料例 |
|---|---|---|---|
| 共通テスト(2021年〜) | 資料文や図を読み取って答える問題が中心 | 一次資料や図像の「読解力」をつける | 『大日本帝国憲法』の原文や年表など |
| 国公立大学の二次論述 | 歴史の流れ+評価・因果まで論じさせる | 因果関係・変化の過程を図や地図で整理 | 鎌倉新仏教の展開図、日清・日露戦争の地図 |
| 総合型・推薦入試 | 志望理由書や小論文でテーマの深掘り | 興味関心のあるテーマに関連する「ビジュアル資料」を引用 | 法隆寺伽藍配置図、浮世絵や屏風の解説 |
たとえば、「日本の宗教文化に興味がある」と志望理由書に書く場合、仏像の変遷や建築様式の図解を資料集から引用すれば、説得力が大きく増します。また、浮世絵や町人文化に関する史料をもとに、「庶民文化の発展」について論じることも可能です。
近年は、大学側も“自分の興味を言語化できる力”を重視しています。そうした背景のもと、資料集の史料や図版は「興味を深め、論じる力を育てるネタ帳」として、まさにうってつけです。
資料集は“入試のその先”までカバーできる、数少ない教材のひとつ。ただ覚えるだけで終わらせず、「使える資料」として活用しましょう。
総括:日本史資料集図説おすすめランキングまとめ
最後に、本記事のまとめを残しておきます。
おすすめ日本史資料集ランキング5選
- 詳説日本史図録(山川出版社)
- 全国多数の高校で採用、信頼性抜群。
- フルカラー・図版豊富・近現代や仏教建築も充実。
- 図説 日本史通覧(浜島書店)
- 圧倒的な図解力。地図・系図・年表で理解が進む。
- 記述対策にも効果的。
- 新詳日本史(浜島書店)
- 解説とビジュアルの融合。テーマ別整理が秀逸。
- 暗記に頼らず理解を深めたい人に最適。
- 日本史資料集(日能研ブックス)
- 歴史をストーリーで学べる構成。
- 短時間の復習や教養書としても活用可。
- 歴史資料館 日本史のライブラリー(清水書院)
- 一次資料・原文・浮世絵などで“考える日本史”が学べる。
- 記述・論述・推薦入試対策に最適。
資料集の効果的な使い方5選
- ① 教科書とセットで使う:
- 因果関係や時代の流れがつながる。
- ② 戦争・条約・文化史は図説で視覚強化:
- 出題頻度が高いので、年表・地図・写真で整理。
- ③ 一問一答の補完に:
- 点の知識を線でつなぎ、論述対応力を強化。
- ④ 模試前はテーマ別復習:
- 外交・宗教・女性史などを整理すれば得点力アップ。
- ⑤ 記述・志望理由書のネタに使える:
- 法隆寺の伽藍配置図や浮世絵など、出典として活用可能。
※全保護者さんに読んで欲しい「勉強法や子育て本のおすすめ」を以下の記事で紹介中。Kindle Unlimitedを使うと全て”無料”で読むことができます。





